災害伝言ダイヤル(171)スマホでの使い方を徹底解説

災害伝言ダイヤル(171)スマホでの使い方を徹底解説
大規模な災害が発生した際、家族と連絡を取る手段として非常に重要な役割を果たすのが、災害用伝言ダイヤルとは何か、そしてその使い方です。特に、多くの方が利用するスマホで171を使う方法を知っておくことは、災害時の安否確認に直結します。この記事では、災害 伝言 ダイヤル 使い方 スマホ版について、音声メッセージの残し方・聞き方から、いざという時に使えない時の原因と対処法、さらには携帯電話会社ごとの違いまで、網羅的に解説します。171の練習・体験利用についても触れるので、ぜひご一読ください。
- 災害用伝言ダイヤル(171)の基本的な使い方
- スマホで録音・再生する際の具体的な操作手順
- 知っておくべき注意点や携帯キャリアごとの違い
- 災害時に備えて事前に家族と準備しておくべきこと
災害 伝言 ダイヤル 使い方 スマホでの基本操作
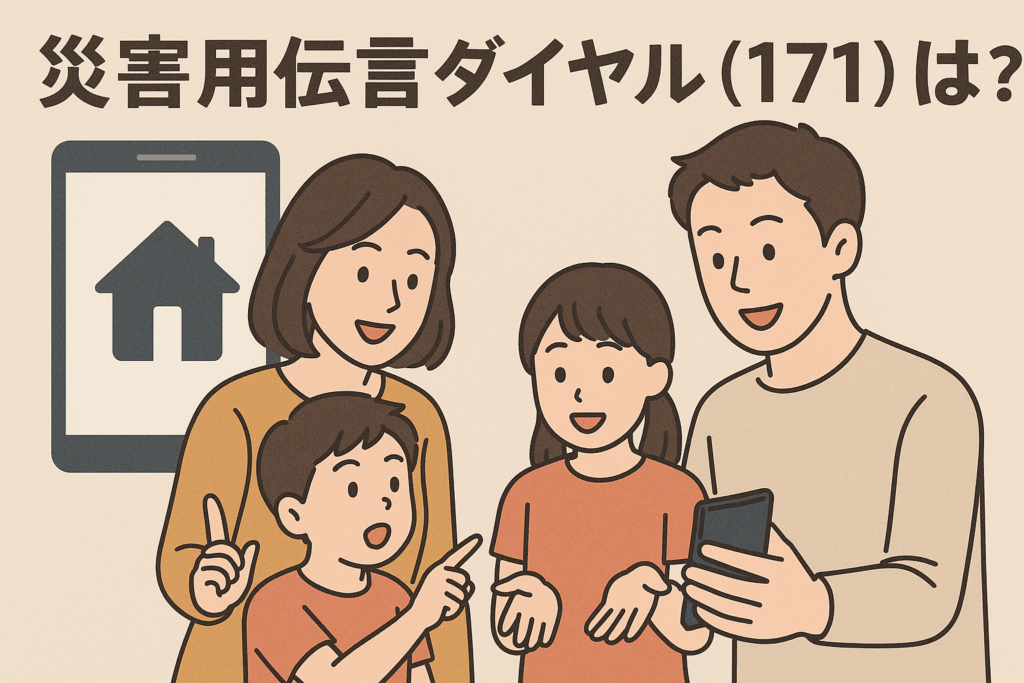
ひかりBOSAIイメージ
- 災害用伝言ダイヤル(171)とは?
- 171 使い方 スマホでの録音・再生方法
- 録音・再生の手順をわかりやすく解説
- 伝言で残すべきメッセージのポイント
- 災害用伝言板(web171)との違い
災害用伝言ダイヤル(171)とは?
災害用伝言ダイヤル(171)とは、震度6弱以上の地震など、大規模な災害が発生した際に、NTT東日本・NTT西日本が提供を開始する声の伝言板サービスです。これは、被災地への電話が殺到することによる通信網のパンク(輻輳状態)を防ぎ、安否確認を円滑にするために作られた仕組みです。
災害発生直後は、被災した家族や友人を心配する電話が特定の地域に集中し、回線が大変混雑して「話中」の状態が続き、まったく電話がつながらなくなります。総務省の報告によると、実際に東日本大震災の直後には、携帯電話事業者によって最大で平常時の約50~60倍以上の通話が一時的に集中しました。
このような状況でも安否確認をスムーズに行えるよう、通信の混雑を避けて全国に分散されたシステムで音声メッセージを預かり、登録・再生できるのが災害用伝言ダイヤル(171)の大きな役割です。被災地の方の電話番号(固定電話または携帯電話)をキーにして、全国どこからでも伝言を残したり、聞いたりすることができます。
サービスのポイント
- 震度6弱以上の大規模災害時に提供される「声の伝言板」
- 被災地への通話集中(輻輳)を避けて安否確認が可能になる
- 被災地の電話番号をキーにしてメッセージを登録・再生する
- NTTが提供するサービスで、公衆電話からの発信など通話料が無料になるケースが多い
171 使い方 スマホでの録音・再生方法
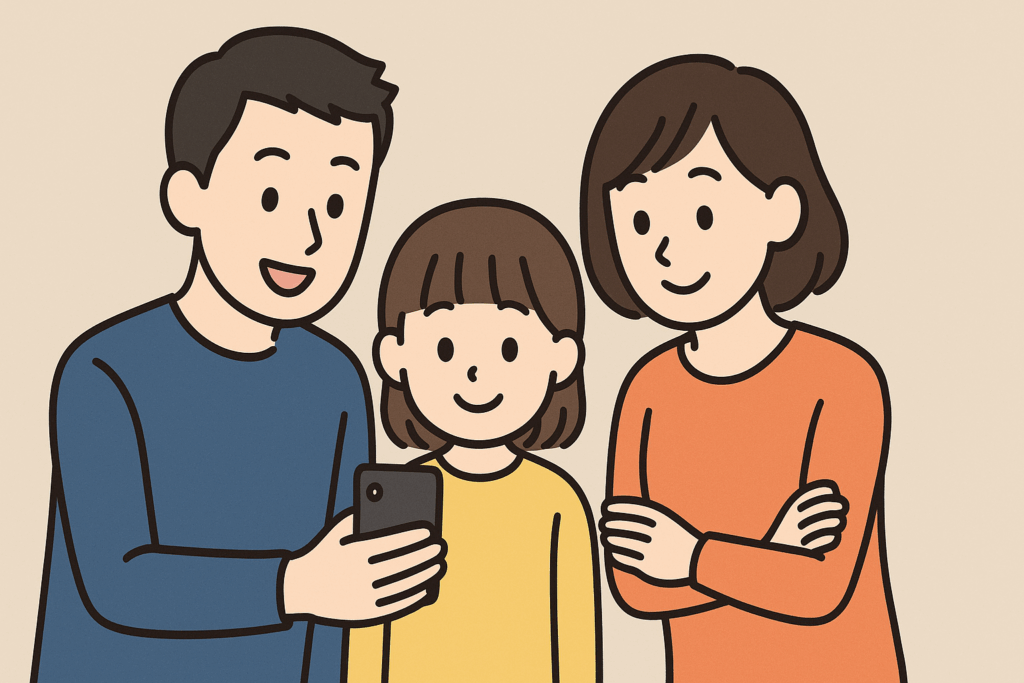
ひかりBOSAIイメージ
スマホから災害用伝言ダイヤルを利用する方法は非常にシンプルです。特別なアプリのインストールは一切不要で、普段お使いの通話アプリから「171」とダイヤルするだけで利用できます。この手軽さは、緊急時において大きなメリットと言えるでしょう。
「171」へダイヤルすると、自動音声ガイダンスが流れます。あとはその指示に従って、スマートフォンのキーパッドで番号を押していくだけで、伝言の録音や再生ができます。プッシュ信号(電話機のボタンを押したときに鳴る「ピッポッパ」という音)が送れるスマホであれば、機種を問わず誰でも簡単に操作することが可能です。
言ってしまえば、手元のスマホを昔ながらの固定電話や公衆電話と同じように使って、伝言を残したり聞いたりするイメージです。操作は簡単ですが、災害時には誰もが動揺してしまうもの。いざという時に「あれ、どうやるんだっけ?」と慌てないよう、後述する体験利用日に一度試しておくことを強くおすすめします。
録音・再生の手順をわかりやすく解説
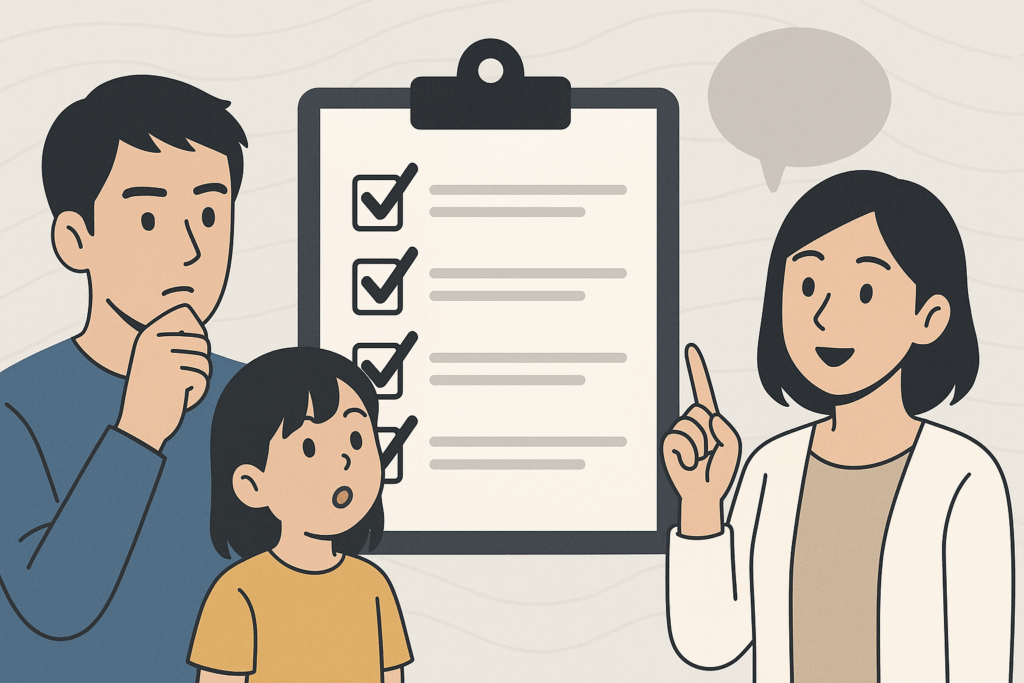
ひかりBOSAIイメージ
災害用伝言ダイヤル(171)の具体的な操作手順を、「伝言を録音する場合」と「伝言を再生する場合」に分けて、より詳しく解説します。また、プライバシーを守るための暗証番号設定についても触れておきます。
伝言を録音する手順
- スマホの通話アプリで「171」に電話をかけます。
- ガイダンスが流れたら、「1」を押します。(録音)
- 連絡を取りたい相手の電話番号を市外局番から正確に入力します。(例:03-XXXX-XXXX)
- 「プッシュ式の電話機をご利用の方は1を押してください」というガイダンスに従い、「1」を押します。
- 「ピッ」という録音開始の合図音の後に、30秒以内でメッセージを録音します。焦らず、はっきりと話しましょう。
- 録音が終わったら「9」を押します。これで録音した内容を聞いて確認できます。
- 内容に問題がなければ、そのまま電話を切れば登録完了です。もし録音をやり直したい場合は、再生中に「8」を押すと再録音が可能です。
録音の注意点
録音開始の合図音の後に、何も話さずにすぐ電話を切ってしまった場合でも、無言の伝言が1件として登録されてしまいます。落ち着いて、合図音を確認してから話すようにしましょう。
伝言を再生する手順
- スマホの通話アプリで「171」に電話をかけます。
- ガイダンスが流れたら、「2」を押します。(再生)
- 安否を確認したい方の電話番号を市外局番から入力します。
- 「プッシュ式の電話機をご利用の方は1を押してください」というガイダンスに従い、「1」を押します。
- 登録されている伝言が新しいものから順に自動で再生されます。
- もう一度同じ伝言を聞きたい場合は「8」を、次の伝言を聞きたい場合は「9」を押します。
- すべての伝言を聞き終わったら、電話を切って完了です。
操作は番号を押すだけなので難しくありませんね。ただ、災害時は冷静な判断が難しいもの。だからこそ事前の練習が大切になります。家族や友人と一緒に試してみるのが一番ですよ。
プライバシーが心配な時は「暗証番号」を設定
「誰でも再生できるのは不安」という場合は、暗証番号を設定して特定の人のみが再生できるようにすることも可能です。録音時に「1」の代わりに「3」を、再生時に「2」の代わりに「4」を押し、ガイダンスに従って4桁の暗証番号を設定・入力します。家族間で事前に暗証番号を決めておくと安心です。
伝言で残すべきメッセージのポイント
伝言の録音時間は1件あたり30秒以内と非常に限られています。短い時間で必要な情報を的確に伝えるため、話す内容をあらかじめ頭の中で整理しておくことが重要です。誰が聞いても状況がわかるように、以下の4つのポイントを必ず含めるようにしましょう。
メッセージに含めるべき4つの要点
- 自分の名前:まず「〇〇です」と、誰からのメッセージか分かるようにはっきりと名乗ります。
- 安否状況:自分や一緒にいる家族などの安否を具体的に伝えます。「無事です」だけでなく、「〇〇と△△と一緒にいて、全員無事です」のように伝えると、聞いた人がより安心できます。
- 現在の場所:どこにいるのか、避難場所などを具体的に伝えます。「避難所にいます」だけでは場所が特定できません。「〇〇小学校の体育館に避難しています」のように、固有名詞を出すのがポイントです。
- 今後の予定:可能であれば、「しばらくここにいます」「次は〇時にまた連絡します」など、今後の簡単な予定を伝えます。これにより、すれ違いを防ぐことができます。
(伝言の例文)
「お母さん、太郎です。僕とおばあちゃんは無事です。今は〇〇中学校の体育館に避難しています。食料も少しあります。また夕方6時頃に連絡します。」
このように、限られた時間の中で「誰が」「どういう状態で」「どこにいるか」という最も重要な情報を正確に伝えることを意識してください。
災害用伝言板(web171)との違い
災害時の安否確認サービスには、「災害用伝言ダイヤル(171)」の他に、「災害用伝言板(web171)」というものもあります。この二つのサービスは密接に連携していますが、利用方法や特徴に違いがあるため、状況に応じて使い分けるのが賢明です。
最も大きな違いは、171が電話回線を使って「音声」で伝言を残すのに対し、web171はインターネット回線を使って「テキスト(文字)」で伝言を残す点です。スマホやパソコンから専用サイトにアクセスし、文字で安否情報を登録・確認できます。
| 項目 | 災害用伝言ダイヤル(171) | 災害用伝言板(web171) |
|---|---|---|
| 伝言形式 | 音声(30秒以内) | テキスト(全角100文字以内) |
| 利用端末 | 電話(固定電話、スマホ、公衆電話など) | PC、スマホ、タブレットなど(要ネット接続) |
| アクセス方法 | 電話番号「171」へダイヤル | 専用サイト「web171.jp」へアクセス |
| 特長 | ネット環境がなくても電話さえ通じれば使える。操作がシンプル。 | 正確な住所や名前など文字で確実に伝えられる。音声が出せない状況でも利用可能。 |
| 連携 | 相互に登録された伝言を確認可能 (171の音声はweb171で音声ファイルとして確認でき、web171のテキストは171で機械音声によって再生される) | |
そして、最も重要なのは、これらのサービスは相互に連携しているという点です。例えば、171で録音された音声メッセージは、web171上で音声ファイルとして再生ボタンを押すだけで確認できます。逆に、web171で登録されたテキストメッセージは、171に電話をかけると、合成音声が読み上げてくれます。避難所が騒がしくて声が聞き取れない時はweb171、ネットが繋がらないけど電話はできる時は171、というように状況に応じて使い分けられるように、両方の存在を覚えておきましょう。

災害 伝言 ダイヤル 使い方 スマホでの注意点と準備
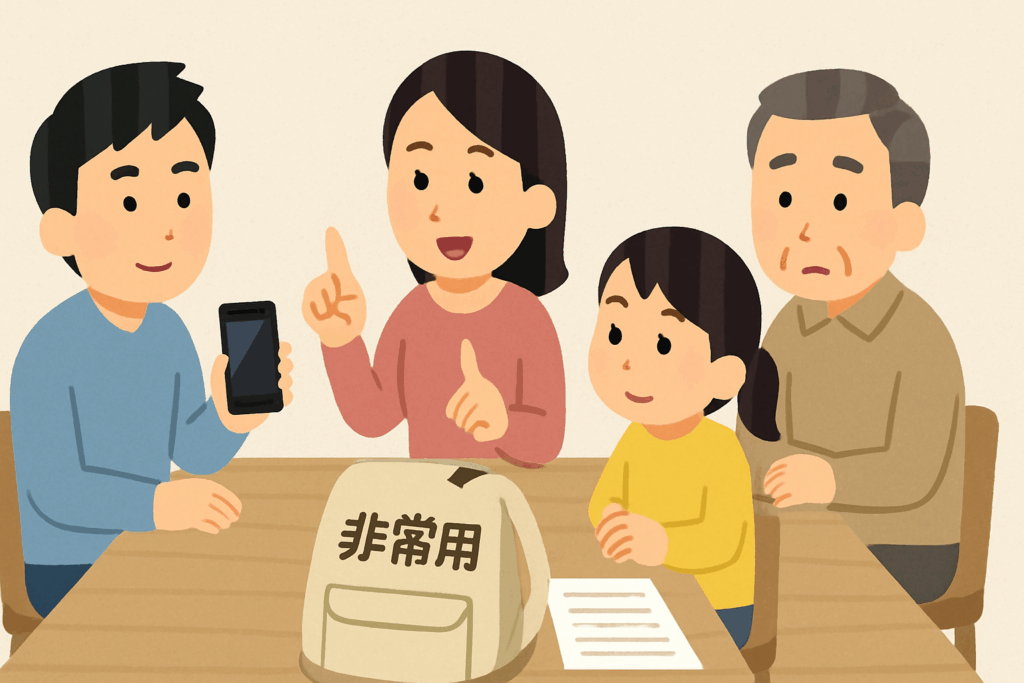
ひかりBOSAIイメージ
- 災害時にサービスが使えない状況とは
- 携帯キャリアごとの対応状況まとめ
- 事前に練習しておくことが重要
- 体験利用できる日をチェックしよう
- 家族で安否確認ルールを決めよう
- 災害 伝言 ダイヤル 使い方 スマホ版を家族で共有
災害時にサービスが使えない状況とは
いざという時に頼りになる災害用伝言ダイヤルですが、万能ではありません。いつでも必ず使えるわけではなく、利用できない、あるいは利用が難しいケースも存在します。
まず大前提として、このサービスはNTTが「大規模な災害が発生し、通信が混雑する恐れがある」と判断した場合にのみ提供が開始されます。そのため、小規模な地震や局地的な豪雨などでは開設されない可能性があります。サービスの提供開始は、テレビ、ラジオ、インターネットのニュースなどを通じて告知されるので、情報を確認することが大切です。
利用できない、または困難な主なケース
- サービス提供期間外:災害が発生していない平常時は、後述する体験利用日以外は利用できません。災害が収束したと判断されるとサービスは終了します。
- 大規模な通信インフラの破壊:システムは全国に分散配置され頑丈に作られていますが、広域にわたる基地局の倒壊や大規模な停電、ケーブルの断線など、通信インフラそのものが甚大な被害を受けた場合は、サービス自体が利用できなくなる可能性があります。
- 伝言の保存期間終了後:登録された伝言は、サービスの提供期間が終了するとすべて削除されます。必要な情報はメモに残しておきましょう。
- 個人のスマホの問題:当然ながら、スマホ本体のバッテリー切れ、故障、水没などの場合は利用できません。
このように、災害用伝言ダイヤルだけに頼るのは危険です。複数の安否確認手段(SNS、他の伝言サービス、集合場所の決定など)を組み合わせて準備しておくことが、本当の意味での防災につながります。
携帯キャリアごとの対応状況まとめ
災害用伝言ダイヤル(171)はNTTが提供するサービスですが、ドコモ、au、ソフトバンクといった各携帯キャリアのスマホからも問題なく利用が可能です。しかし、契約しているキャリアやプランによっては若干対応が異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
| キャリア | 災害用伝言ダイヤル(171) | 災害用伝言板(キャリア提供) | 備考 |
|---|---|---|---|
| NTTドコモ | 利用可能 | あり | ahamoでは一部機能(登録お知らせメール等)に制限あり。 |
| au (KDDI) | 利用可能 | あり | povo、UQ mobile契約者は安否情報の登録はできず、確認のみ可能。登録はweb171を利用。 |
| ソフトバンク | 利用可能 | あり | ワイモバイルも同様に利用可能。 |
| 楽天モバイル | 利用可能 | あり (web171の利用を推奨) | 安否登録は、音声の171よりもインターネット経由のweb171を推奨しています。 |
※2025年10月1日現在の情報です。詳しくは各キャリアのホームページにてご確認ください。
大手4キャリアでは基本的に利用できますが、格安SIM(MVNO)を利用している場合は特に注意が必要です。多くの事業者は対応していますが、一部非対応の可能性もゼロではありません。ご自身の契約している通信会社の公式サイトで「災害時の対応」について一度確認しておくことを強くおすすめします。
前述の通り、楽天モバイルや一部のau系サービス(povo、UQ mobile)では、音声の171よりもテキスト版のweb171の利用が推奨されています。これは、各社のネットワーク構成やサービス体系によるものです。ご自身のプランではどちらが適しているか、平時のうちに把握しておきましょう。
事前に練習しておくことが重要
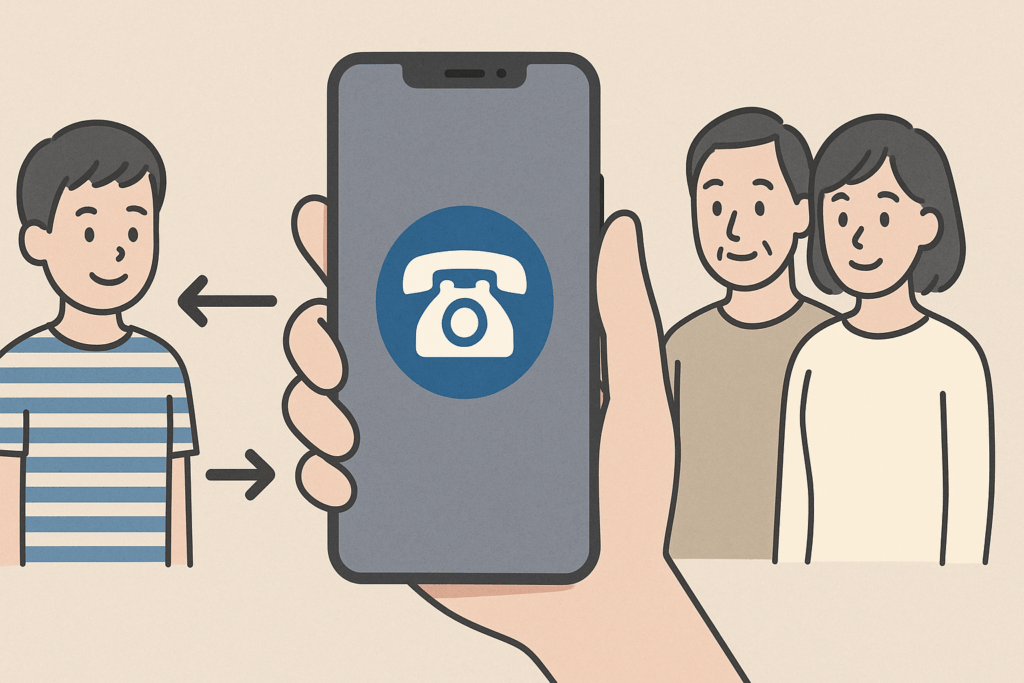
ひかりBOSAIイメージ
災害は、私たちの都合などお構いなしに、ある日突然やってきます。強い揺れや混乱の中でパニック状態に陥り、普段なら簡単にできるはずの操作すら冷静に行うのは非常に困難です。だからこそ、災害用伝言ダイヤルの使い方は、事前に一度でも練習しておくことが極めて重要になります。
「使い方の手順は読んだから大丈夫」と思っていても、いざという時には肝心な連絡先の電話番号を思い出せなかったり、ガイダンスのどの番号を押せばいいか分からなくなったりするものです。一度でも実際に体験しておけば、その差は歴然ですよ。
幸いにも、このサービスには後述する「体験利用日」が定期的に設けられています。家族や親しい友人と日時を合わせて、「今、地震が起きたと想定して、お父さんの携帯にメッセージを残してみよう」といった形で、実際にメッセージの録音と再生を試してみてください。たった一度の練習が、万が一の時にあなたと大切な人の命綱になるかもしれません。
体験利用できる日をチェックしよう
災害用伝言サービスは、災害時以外にも国民の防災意識向上のため、定期的に無料で体験利用ができる機会が設けられています。もしもの時に備え、この貴重な機会を積極的に活用して使い方に慣れておきましょう。(参照:NTT東日本 災害用伝言ダイヤル(171))
主な体験利用可能日
- 毎月1日、15日(0:00~24:00)
- 正月三が日(1月1日 0:00~1月3日 24:00)
- 防災とボランティア週間(1月15日 9:00~1月21日 17:00)
- 防災週間(8月30日 9:00~9月5日 17:00)
※期間は変更される場合があります。また、地域の防災訓練に合わせて利用可能になることもあります。
これらの日に「171」にダイヤルすると、「こちらは災害用伝言ダイヤル、体験利用センタです」というアナウンスが流れます。操作手順は実際の災害時とほぼ同じです。スマートフォンのカレンダーに「171体験日」として登録しておくなどして、年に一度は家族で防災について話し合うきっかけにするのも良いでしょう。
家族で安否確認ルールを決めよう
災害用伝言ダイヤルの使い方を個人で覚えること以上に重要なのが、家族や大切な人との間で「安否確認のルール」を事前に決めておくことです。せっかく伝言を残しても、聞くべき相手がその方法を知らなければ意味がありません。
災害発生時、家族がそれぞれ別の場所(会社、学校、外出先など)にいる可能性は十分に考えられます。その際に、「誰の電話番号に伝言を残すか」という中心軸を決めておかなければ、お互いの安否を効率よく確認することができません。
事前に決めておくべき安否確認ルールの例
- キーとなる電話番号の統一:
安否確認の伝言を残す・聞くための中心となる電話番号を一つだけ決めます。(例:「災害時は、固定電話ではなく、お父さんの携帯番号『090-XXXX-XXXX』にみんなで登録・確認しよう」) - 連絡手段の優先順位付け:
まず何で連絡を試みるか、複数の手段と優先順位を決めておきます。(例:①災害用伝言ダイヤル/伝言板 → ②LINEのグループ通話 → ③個別のSMS) - 集合場所の複数確認:
万が一連絡が取れない場合に備え、地域の避難場所(第一候補)、少し離れた親戚の家(第二候補)など、複数の集合場所候補を確認し、地図アプリなどで共有しておきます。 - 遠方の親戚を中継点に:
被災地から遠く離れた親戚や友人を「連絡の中継点」と決め、そこへ各自が連絡を入れるというルールも有効です。
これらのルールを平常時に家族会議などでしっかりと話し合い、紙に書いて冷蔵庫に貼ったり、スマホのメモに保存したりして、全員がいつでも確認できるようにしておくことが、災害時の迅速で確実な安否確認につながります。
災害 伝言 ダイヤル 使い方 スマホ版を家族で共有
この記事では、スマホでの災害用伝言ダイヤル(171)の使い方から、事前の備えまで詳しく解説しました。最後に、記事の重要なポイントをリスト形式でまとめます。この情報をぜひ家族や大切な人と共有し、万が一の災害に備えてください。
この記事をブックマークし、使い方と家族ルールを定期的に確認しよう
災害用伝言ダイヤルは震度6弱以上の災害時に開設される音声の伝言板サービス
スマホの通話アプリから「171」をダイヤルするだけで特別なアプリは不要
ガイダンスに従い録音は1番、再生は2番を選択して操作する
伝言は1件につき30秒以内なので要点を簡潔に話すことが大切
メッセージには必ず「自分の名前」「安否状況」「現在の場所」を含める
web171はインターネットで利用するテキスト版のサービスで171と相互に連携している
原則として大規模災害時に開設され平常時は体験利用日以外は使えない
大規模な通信インフラ障害やスマホのバッテリー切れなど使えない状況も想定しておく
楽天モバイルやpovo、UQ mobileなど一部サービスはweb171の利用が推奨されている
格安SIMユーザーは契約会社が171に対応しているか公式サイトで事前の確認が安心
災害時の混乱の中でも冷静に操作できるよう事前の練習がとても大切
毎月1日と15日など定期的に体験利用ができる日が設けられているので活用しよう
家族で安否確認のキーとなる電話番号を一つに決めておくことが最も重要
連絡手段の優先順位や複数の集合場所もあらかじめ話し合っておく

「何を・どれだけ備えればいいかわからない…」そんなお悩みに、防災士が最適な備蓄計画を提案します。
- ✔ 人数・日数に応じた備蓄量を試算
- ✔ 防災倉庫や企業BCP対策の相談OK
- ✔ 無料で初回アドバイス
- ✔ BCP対策・防災倉庫向けカタログを送付










コメント