福島の被災者が考える備蓄

福島の被災者が考える備蓄
株式会社ヒカリネット HIH 防災士 後藤秀和
災害時に備えることは、日々の安心を作るために非常に重要です。この記事では、家庭や企業で必要な備蓄品や防災対策の基本を詳しく解説します。
災害はいつ訪れるかわからないため、日常の中で備えておくことが大切です。備蓄は単なる物品の確保ではなく、家族や社員の心の準備も含まれます。
さらに、備蓄を通じてコミュニケーションを深め、緊急時における役割分担を話し合っておくことも重要です。これにより、災害時に全員が冷静に行動できるようになり、安心して生活をするための基盤を築くことができます。日常の中で、備えの意識を持つことは、心の余裕を生み出し、家族や組織の結束力を高めます。
備蓄品と避難用は別にすべき

東日本大震災を経験した私は、「備蓄品と避難用は別にすべき」だと痛感しています。震災当日、家具が倒れ物が散乱し、必要品にも手が届きませんでした。命を守るためには、災害直後にすぐ持ち出せる避難用リュックと、長期備蓄を分けて準備することが不可欠です。
長期備蓄は、水や食料、トイレットペーパー、カセットコンロなど長期間の生活を支える品で、量も多くかさばります。一方で避難用リュックは、懐中電灯やモバイルバッテリー、携帯トイレ、非常食、常備薬、防寒具など数日間をしのぐための必需品を、軽く持ち運びやすくまとめるものです。両者を一緒にすると、災害時に「どこに何があるかわからない」「重くて持てない」という混乱を招きます。
避難用リュックは玄関など手に取りやすい場所に置くことが重要です。長期備蓄は収納にまとめ、避難用はすぐ持ち出せるようにしておく。この区別が安全と安心を高めます。家族、社員構成によって必要な物も異なるため、子どもや高齢者、ペットがいる家庭は特に個別の準備が求められます。
家庭で用意をしておきたい備蓄品9選(4人家族の場合)(参考価格相場)
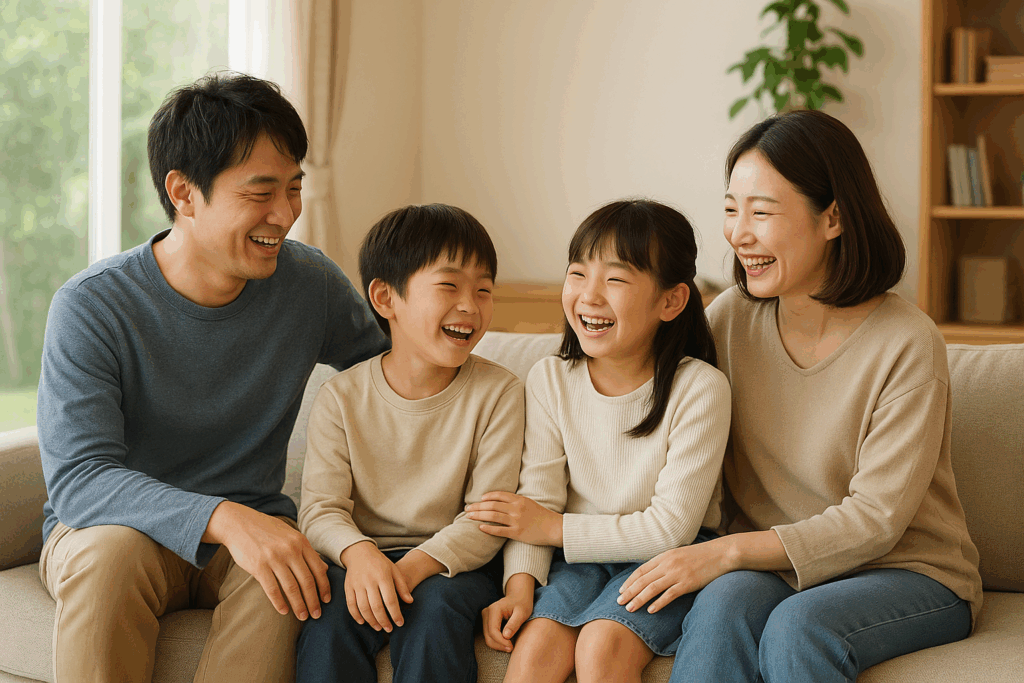
- 保存水(30L)(3,000円)
2Lのボトルを箱で用意しましょう。また、災害直後に水道が出る場合は浴槽に満杯まで水をためましょう。数時間、数日後に断水することもよくあります。浴槽は洗わなくても大丈夫です。主にトイレを流すのに使用します。
- アルファ米(30食)(10,000円)
電子レンジは使えない前提で考えましょう。白米だけでなく数種の味を用意しましょう。
- 缶詰(10食)(2,000円)
魚や野菜などお好みで。フルーツがあっても良いでしょう。
- 簡易トイレ(60回分)(3,000円)
家庭の便器を使用して凝固消臭する粉末タイプを用意しましょう。
- ウェットティッシュ(100枚)(500円)
断水時には必須です。特に小さいお子さんがいる場合には強力な助けになります。
- 生理用品(1回分)(500円)
災害時に最も不足する品のひとつです。
- 使い捨ての食器、割り箸と食品用ラップ(食器は10枚)(500円)
洗えない、ゴミを出せない前提で再利用します。紙皿等はラップで包み、使用後はラップのみ捨てます。
- ラジオ(単3電池使用か発電可能なもの)(1000円~)
停電し、Wi-Fi、5G、4G全て止まった場合、唯一の情報源になります。単1、単2電池は東日本大震災時には日本中で品切れになりました。
- 給水バッグ(2L~3Lのものか背負えるもの)(1000円~)
断水時、給水車から自宅に運ぶのに必要ですが、大容量は注意が必要です。特にマンションの上層階に運ぶ場合、大変な思いをします。背負えるタイプが理想です。
企業が用意をしておきたい備蓄品9選(従業員100人の場合)(参考価格相場)

- 保存水(900L)(10万円)
2Lが6本入りのケースで70~80箱分になります。6箱1列に積んでも2㎡に収まります。
- アルファ米(900食)(30万円)
食器不要の水だけでおにぎりができるタイプがあります。おすすめです。
- 簡易トイレ(1800回分)(10万円)
粉末凝固タイプでの対応ができればベストです。トイレ数が少ないオフィスの場合は、ダンボール型の仮設トイレの検討も必要です。
- トイレットペーパー(300ロール)(1万円)
トイレ以外にも利用できるため、1人あたり3ロール用意しましょう。
- ラジオ(10台)(1万円)
情報封鎖時に社員を帰宅させるかどうかの重要な判断基準になります。可能な限り地域密着性の高いチャンネルを使用します。予算は上がりますがライト付きでスマホ充電ができるタイプが理想です。
- 医薬品
一般的な配置薬が理想的です。備蓄意識が無くとも補充してくれますから契約をお勧めします。
- 生理用品(女性社員人数×1回分)
担当者が男性の場合は女性スタッフに相談しましょう。一般男性の想像よりも大量に必要です。
- 寝袋(100セット)(100万円)
毛布だけでの社内泊は現実的ではありません。廊下や床で寝ることを想定しましょう。防災用のコンパクトなシュラフがおすすめです。
- ブルーシート(5m×7mくらいのサイズを10枚)(5万円)
仮設トイレの目隠し、破損した窓の保護、浸水対策等、床敷き以外にも用途は多様です。併せてビニールテープも用意しましょう。強力であればガムテープでも良いです。
備蓄品の収納・管理方法

備蓄品は「備えて終わり」ではなく、収納と管理が命を守る鍵です。
家庭の場合は食料や飲料水、衛生用品などは透明ケースに入れ、重いものは低い位置に置き、大きくラベルを貼って誰でも分かるようにします。玄関やリビングなど家族がすぐ手に取れる場所に置き、水や懐中電灯は寝室や車内などにも分散させると安心です。
企業の場合は社員数や勤務体制に応じて必要量を明確にし、食品・水・衛生用品・簡易トイレ・防寒具・救急用品・情報機器などを用途ごとに分けて保管します。大型の備蓄は倉庫や専用スペースにまとめます。各フロアや出入口付近に分散配置することが重要です。棚やケースには内容物と数量、賞味期限をラベル表示し、停電時にも取り出しやすいよう通路を確保します。
期限切れ防止には、賞味期限や使用期限を一覧表やスマホに記録し、消費と補充を繰り返す「ローリングストック法」が有効です。年に一度の点検日を決め、状況に合わせて必要量を見直し、ライトやラジオも動作確認します。
自宅や会社に留まるか、避難するかの判断基準

家屋、社屋の損傷具合や周囲の状況から、避難の必要性を判断します。建物が安全であれば、留まることも選択肢の一つです。避難情報や警報を定期的に確認し、迅速な判断を心がけましょう。留まる場合は、ラジオやスマホで情報収集を欠かさず行い、万が一の避難に備えておくことが重要です。さらに、隣近所との連携を図り、助け合える体制を築くことも大切です。共助の精神を持ち、災害時においても地域全体で協力し合うことが、危機を乗り越える力となります。
- 避難する場合の準備:備蓄だけでは不十分?
避難する際には、持ち運びが容易な防災リュックが役立ちます。公共交通機関が利用できない可能性もあるため、徒歩での移動を想定した計画を立てておくことも重要です。避難場所に到着するまでに必要な時間や体力を考慮し、無理のないペースで行動できるよう準備を整えましょう。
- 防災リュックの重要性とその内容
防災リュックは、すぐに持ち出せるように準備しておくことが重要です。中には、非常食、懐中電灯、携帯充電器、救急セットなどを入れておくと良いでしょう。これらは、避難時に必要な最低限のアイテムです。防災リュックは一人一つ用意し、全員がどこにあるかを確認しておくことが大切です。防災リュックの準備は、単なる物品の確保にとどまらず、心の備えを強化することにもつながります。

- 避難先で役立つアイテムとその準備方法
避難所での生活を考慮し、携帯トイレや携帯食なども準備しておくと安心です。これらは防災リュックに入れておくと良いでしょう。事前に避難所の場所やルートを確認し、全員が把握しておくことが大切です。避難所での生活の質を向上させるために、必要なものをリストアップし、余裕を持った準備を心がけましょう。

まとめ
備蓄品は日常的に管理し、家庭内、社内で収納場所や使い方を共有することが大切です。こうした工夫が非常時の混乱を防ぎ、安心して行動できる備えとなります。 災害時に必要な備蓄品は多岐にわたりますが、まずは水、食料、衛生用品、医薬品を最低限備えておきましょう。これらは、数日間の避難生活を支えるために不可欠です。災害時には、普段の生活と異なる状況に直面するため、精神的な負担も増えることがあります。備蓄品を揃える際には、アレルギーも考慮し、ストレスを軽減できるよう工夫しましょう。あらゆるシナリオを想定し、柔軟に対応できる体制を整えることが、安心した生活を送るための鍵となります。






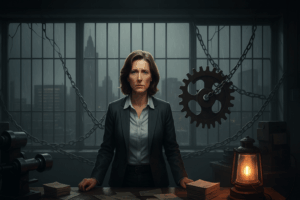
コメント