防災リュックの食料おすすめは?選び方と量を解説

防災リュックの食料おすすめは?選び方と量を解説
災害に備えて防災リュックの準備を進める中で、多くの人が悩むのが食料の選び方ではないでしょうか。防災リュックに入れる食料について、おすすめは何日分で、どれくらいの量が必要なのか、具体的に考えるのは難しいかもしれません。また、非常食の持ち歩きにおすすめなものや、スーパーで揃える非常食、長期保存できる食品のランキングで人気のものは何か、気になる点は多いでしょう。防災グッズの食料としておすすめのものは何か、普段の食品で非常食になるもの、そして防災食で最強なのはどんなタイプか、備蓄食料をスーパーでおすすめ品から選ぶ際のポイントまで、この記事で詳しく解説します。
- 防災リュックに入れるべき食料の具体的な日数と量の目安がわかる
- 調理不要で便利な最強の非常食の種類がわかる
- スーパーで手軽に揃えられる備蓄食料の選び方がわかる
- 持ち歩きに便利な携帯食や長期保存できる食品がわかる
防災リュックの食料、おすすめの量と選び方

ひかりBOSAIイメージ
- 防災リュックの食料は何日分必要?
- 防災リュックに入れる食料の量の目安
- 防災食で最強なのは調理不要なもの
- 防災グッズの食料としておすすめのものは?
- 普段の食品で非常食になるもの
防災リュックの食料は何日分必要?
結論から言うと、防災リュックに入れる食料は最低でも3日分、可能であれば1週間分の準備が推奨されています。これは、災害発生後のライフライン(電気・ガス・水道)の復旧や、支援物資が届くまでに時間がかかることを想定しているためです。
農林水産省の「災害時に備えた食品ストックガイド」でも、大規模災害時には1週間以上の備蓄が望ましいとされています。まずは非常用持ち出し袋(一次避難用)に3日分を入れ、自宅での備蓄(二次避難用)として残りの4日分を備えるというように、段階的に準備を進めるのが現実的でしょう。
備蓄日数の考え方
最低3日分: 災害発生直後から公的な支援が本格化するまでを乗り切るための量。
推奨1週間分: ライフラインの復旧が遅れたり、物流が滞ったりする大規模災害に備えるための量。
災害の規模や住んでいる地域の状況によって必要な日数は変動しますが、まずは「3日間」を目標に食料を揃え、そこから少しずつ増やしていくことをおすすめします。
防災リュックに入れる食料の量の目安
必要な日数がわかったところで、次に考えるべきは具体的な「量」です。食料の量は、「必要なエネルギー(カロリー)」と「水分」の2つの観点から考えることが重要です。
1日に必要なエネルギー量
体力を維持し、災害時を乗り切るためには適切なカロリー摂取が欠かせません。活動量によって変動しますが、一般的に推奨される1日あたりのエネルギーの目安は以下の通りです。
- 成人男性:約2,000kcal〜2,200kcal
- 成人女性:約1,500kcal〜1,800kcal
これはあくまで目安であり、子どもや高齢者がいるご家庭では、年齢や体調に合わせて調整する必要があります。非常食を選ぶ際は、パッケージに記載されている栄養成分表示を確認し、カロリー計算をしながらリュックに詰めていきましょう。
1日に必要な水分量

ひかりBOSAIイメージ
飲料水は生命維持に不可欠です。1人あたり1日3リットルを目安に準備しましょう。この量には、飲み水だけでなく、調理や簡単な衛生管理に使用する分も含まれています。
水は重くてかさばるので、すべてをリュックに入れるのは大変かもしれません。最低でも1日分の1人1リットル程度をリュックに入れ、残りは自宅や車などに分散して備蓄しておくと良いでしょう。
| 家族構成 | 必要な食事の数 | 必要な飲料水 |
|---|---|---|
| 大人1人 | 9食 | 9リットル |
| 大人2人 | 18食 | 18リットル |
| 大人2人+子ども1人 | 27食 | 27リットル |
この表を参考に、ご自身の家族構成に合わせた量を準備してください。
防災食で最強なのは調理不要なもの
非常食には様々な種類がありますが、防災食として最強なのは「調理不要でそのまま食べられるもの」です。災害時は電気やガスが使えず、貴重な水を調理に使うことも避けたい状況が考えられます。
調理不要の非常食には、以下のようなメリットがあります。
- ライフラインが止まっても食べられる:火や電気を使わずに栄養補給ができます。
- 水を節約できる:飲料水を調理に使う必要がなく、水分補給に集中できます。
- 手間がかからない:心身ともに疲弊している災害時に、すぐに食べられる手軽さは大きな助けとなります。
- ゴミが少ない:調理器具を使わないため、洗い物が出ず衛生的です。
お湯を注ぐだけで食べられるアルファ米なども非常に優れた非常食ですが、防災リュックに入れておく「一次避難用」の食料としては、まず調理不要のものを優先的に揃えることを強くおすすめします。
具体的には、ゼリー飲料、ようかん、缶詰パン、バランス栄養食などがこれにあたります。これらは開封するだけですぐに食べられるため、避難直後の混乱した状況でも確実にエネルギーを摂取できます。
防災グッズの食料としておすすめのものは?

調理不要で、かつ栄養価が高い具体的な食品をいくつか紹介します。これらは防災グッズの食料として非常に優れており、多くの防災セットにも採用されています。
井村屋 えいようかん
1本でご飯一杯分(約171kcal)のエネルギーを手軽に補給できる、まさに「食べる非常食」です。公式サイトによると5年間の長期保存が可能で、コンパクトなため持ち歩きにも適しています。適度な甘さが、災害時のストレスを和らげる効果も期待できます。
長期保存 inゼリー エネルギー ロングライフ
inゼリーの長期保存タイプで、製造から3年の保存が可能とされています。食欲がない時でも水分とエネルギー(1個あたり200kcal)を同時に補給できるのが最大の強みです。子どもから高齢者まで、全世代におすすめできます。
カロリーメイト ロングライフ
バランス栄養食の定番、カロリーメイトにも3年保存可能なロングライフタイプがあります。1箱で400kcalを摂取でき、ビタミンやミネラルも補給できるとされています。コンパクトでかさばらない点も防災リュック向きです。
アレルギーに関する注意
非常食を選ぶ際は、必ず原材料を確認し、家族にアレルギーを持つ人がいる場合は、アレルギー対応の製品を選びましょう。最近では、特定原材料等28品目不使用の非常食も多数販売されています。
普段の食品で非常食になるもの
特別な非常食を買い揃えるだけでなく、普段の食生活で使っている食品の中にも非常食になるものはたくさんあります。これを意識することで、「ローリングストック」という備蓄方法が実践しやすくなります。
ローリングストックとは、普段から少し多めに食材を買い置きし、賞味期限の古いものから消費して、使った分だけ新しく買い足していく方法です。これにより、常に一定量の食料を備蓄しつつ、食品ロスを防ぐことができます。
ローリングストックにおすすめの食品
- 缶詰:サバ缶、ツナ缶、フルーツ缶など。調理不要でそのまま食べられます。
- レトルト食品:カレーや丼ものの素など。温めずに食べられるタイプを選ぶとさらに便利です。
- 乾麺:パスタやうどん、そうめんなど。カセットコンロがあれば調理可能です。
- 栄養補助食品:シリアルバーやプロテインバー。手軽なエネルギー補給源になります。
- お菓子:チョコレート、ナッツ、ドライフルーツなど。高カロリーで気分転換にも役立ちます。
これらの食品は、日常的に消費しながら備蓄できるため、いざという時にも食べ慣れた味で安心感を得られるというメリットがあります。

具体的な防災リュックの食料おすすめリスト

ひかりBOSAIイメージ
- スーパーで揃える非常食のポイント
- 備蓄食料はスーパーで買うのがおすすめ
- 持ち歩きにおすすめの非常食は?
- 非常食長持ちランキング上位の食品
- 【結論】防災リュックの食料のおすすめ
スーパーで揃える非常食のポイント
非常食は防災用品専門店だけでなく、身近なスーパーでも十分に揃えることが可能です。スーパーで選ぶ際のポイントは、「ローリングストック」を前提に、複数の種類をバランス良く組み合わせることです。
スーパーでの非常食選びの4つのポイント
- 主食を確保する:パックご飯、カップ麺、乾麺、シリアルなどを選びましょう。
- 主菜・副菜を選ぶ:缶詰(魚、肉)、レトルト食品、フリーズドライのスープなどを組み合わせ、栄養バランスを考えます。
- 調理不要のものを加える:そのまま食べられる魚肉ソーセージ、チーズ、ナッツなどを加えます。
- 心の栄養も忘れずに:チョコレートやクッキー、スナック菓子など、好きなものもいくつか入れておくと、ストレス軽減に繋がります。
スーパーで購入する際は、賞味期限を必ず確認し、最低でも半年から1年以上あるものを選ぶようにしましょう。また、缶詰は缶切り不要のプルトップ式を選ぶなど、災害時の使いやすさも考慮することが大切です。
備蓄食料はスーパーで買うのがおすすめ
前述の通り、備蓄食料をスーパーで購入することには多くのメリットがあります。最大の利点は、「手軽さ」と「経済性」です。
普段の買い物のついでに少しずつ買い足せるため、無理なく備蓄を始められます。また、特売などを利用すれば、防災専用の非常食をまとめて購入するよりもコストを抑えられる場合があります。
さらに、日常的に食べている商品を備蓄することで、家族の好みに合った食料を揃えやすく、災害時でも普段に近い食生活を送れるため、精神的な負担を軽減する効果も期待できるのです。
スーパーで買う際の注意点
一方で、スーパーで販売されている一般的な食品は、防災専用の長期保存食に比べて賞味期限が短い傾向にあります。そのため、定期的な賞味期限のチェックと入れ替えが不可欠です。スマートフォンのリマインダー機能などを活用し、管理を怠らないようにしましょう。
持ち歩きにおすすめの非常食は?

ひかりBOSAIイメージ
防災リュックに入れるだけでなく、普段使っているカバンにいくつか入れておきたいのが「携帯用非常食」です。外出先で災害に遭遇する可能性も考えて、持ち歩きにおすすめの非常食を準備しておきましょう。
選ぶポイントは、「軽量・コンパクト」「高カロリー」「調理不要」の3点です。
- ようかん:井村屋の「えいようかん」は、コンパクトで高カロリー、長期保存可能と、携帯食の条件を完璧に満たしています。
- シリアルバー・栄養補助食品:1本で手軽にエネルギーを補給でき、腹持ちも良いのが特徴です。
- チョコレート:高カロリーで糖分が脳の栄養になります。夏場でも溶けにくいタイプを選ぶと良いでしょう。
- ドライフルーツ・ナッツ:ビタミンやミネラルを補給でき、自然な甘みや食感が楽しめます。
私は普段からカバンにシリアルバーとミニようかんを入れています。小腹が空いた時のおやつにもなりますし、いざという時のお守りにもなるので一石二鳥ですよ。
これらの携帯食をジッパー付きの袋などにまとめてカバンに入れておけば、いつでもどこでも最低限のエネルギー補給が可能になります。
非常食長持ちランキング上位の食品

ひかりBOSAIイメージ
ローリングストックとは別に、管理の手間を減らしたい方には、やはり5年以上の長期保存が可能な非常食がおすすめです。これらの食品は、一度購入すれば頻繁な買い替えが不要になるため、防災備蓄のベースとして非常に頼りになります。
一般的に、非常食として長持ちするランキングの上位に来るのは以下のような食品です。
| 種類 | 代表的な商品 | 一般的な保存期間 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| アルファ米 | 尾西食品シリーズ、サタケ マジックライス | 5年 | お湯や水でご飯に戻る。軽量で種類が豊富。 |
| 缶詰パン | パン・アキモト「パンのかんづめ」 | 5年 | 開けてすぐに柔らかいパンが食べられる。 |
| 保存水 | 各社から販売 | 5年~15年 | 長期保存用に処理された飲料水。 |
| フリーズドライ食品 | 永谷園フリーズドライご飯 | 7年 | お湯で戻すタイプ。軽量で味の再現度が高い。 |

保存期間を統一するメリット
可能であれば、備蓄する長期保存食の賞味期限(保存期間)を「5年」などに統一すると、管理が非常に楽になります。「次の買い替えは5年後」と覚えておけば、個別の賞味期限を細かくチェックする手間が省けます。
これらの長期保存食を基本の備えとしつつ、スーパーで購入した食品でローリングストックを組み合わせるのが、最も効率的で安心な備蓄方法と言えるでしょう。
【結論】防災リュックの食料のおすすめ
これまでの情報をまとめると、防災リュックに入れる食料は、多様な状況を想定してバランス良く準備することが重要です。最後に、この記事の要点をリスト形式で振り返ります。
- 防災リュックに入れる食料は最低3日分、できれば1週間分を用意する
- 1日の摂取カロリー目安は成人男性で約2,200kcal、女性で約1,800kcal
- 飲料水は1人1日3リットルを目安に備蓄する
- 最強の防災食は火も水も使わない「調理不要」の食品
- 調理不要の食品としてはようかんやゼリー飲料が特に優秀
- アレルギー対応の非常食も忘れずにチェックする
- 普段の食品も「ローリングストック」で立派な非常食になる
- スーパーでは缶詰やレトルト食品、乾物などを少し多めに買う
- スーパーでの備蓄は手軽だが賞味期限管理が重要
- 普段のカバンにも軽量コンパクトな携帯食を入れておく
- 携帯食にはようかんやシリアルバーがおすすめ
- 管理を楽にするなら5年以上の長期保存食をベースに揃える
- アルファ米や缶詰パンは長期保存食の定番
- 長期保存食は賞味期限を統一すると管理がしやすい
- 長期保存食とローリングストックの組み合わせが理想的
防災士の経験から生まれた、信頼できる備え。
経験が語るHIHの「本当に必要な防災セット」。

「何を・どれだけ備えればいいかわからない…」そんなお悩みに、防災士が最適な備蓄計画を提案します。
- ✔ 人数・日数に応じた備蓄量を試算
- ✔ 防災倉庫や企業BCP対策の相談OK
- ✔ 無料で初回アドバイス
- ✔ BCP対策・防災倉庫向けカタログを送付









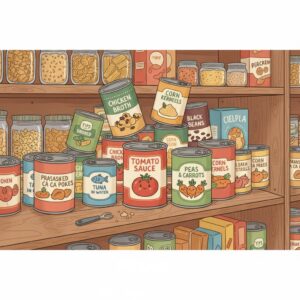





コメント